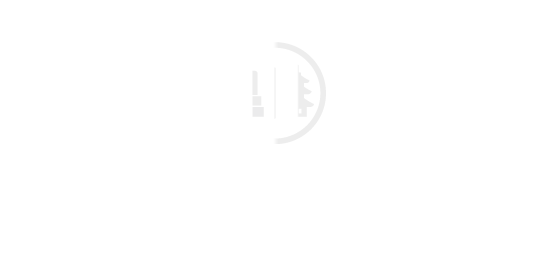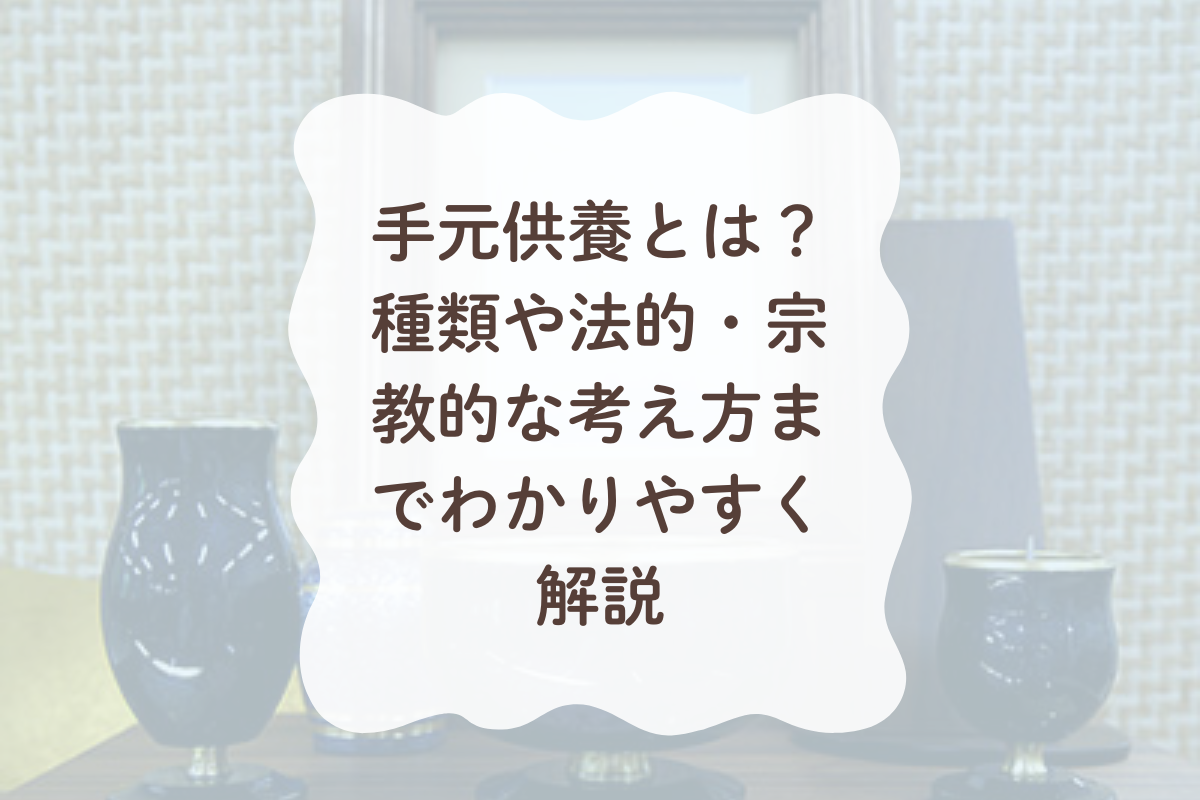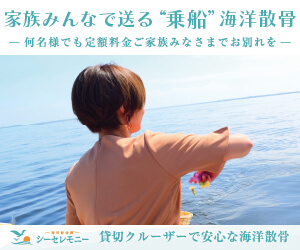大切な人を亡くしたあと、その人の存在を身近に感じながら暮らしていきたい——。
そんな想いを叶える方法の一つとして、近年注目されているのが「手元供養(てもとくよう)」です。
この記事では、手元供養の基本的な意味や種類、法的・宗教的な側面について、わかりやすくご紹介します。
手元供養とは?
手元供養とは、故人の遺骨の一部を自宅など身近な場所に保管し、供養する方法です。2000年代に入ってから広まり始め、現在では多くの人が選択する供養のかたちとなっています。
たとえば、自宅の仏壇の横に小さな骨壺を置く方法や、遺骨の一部をペンダントにして身に着ける方法などがあります。
手元供養と自宅供養の違い
「手元供養」と似た言葉に「自宅供養」がありますが、この2つは、次のように区別できると思っています。
| 区分 | 手元供養 | 自宅供養 |
| 遺骨の量 | 一部(分骨) | 全骨 |
| 容器のサイズ | 小さなミニ骨壺 | 一般的な骨壺(5〜7寸) |
| 目的 | 故人を身近に感じたい | お墓の代わりに保管 |
| 保管場所 | 仏壇の横やアクセサリーにするなど | 仏壇の横や自宅内の安置スペース |
手元供養は、あくまで「お墓や納骨堂に納める予定の遺骨の一部を、分けて自宅に置いて供養する方法」です。「お墓が不要だから手元供養をする」という方はごくわずかで、そうしたケースでは全骨を安置する自宅供養を選ばれることが多いです。

手元供養

自宅供養
手元供養は法的・宗教的に問題ない?
法律について
手元供養や自宅供養は、法律上まったく問題ありません。
ただし「遺骨を埋葬する場合」に限っては、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」により、都道府県の認可を受けた墓地でなければならないと定められています。
つまり、自宅の庭などに埋めるのはNGですが、骨壺に入れて自宅に置いておくことは合法です。
なお、こちらは人骨の場合であり、ペット等はこの通りではありません。
仏教的な考え方
仏教では、四十九日を過ぎると故人は浄土に生まれ変わり、仏様になると考えられています。そのため、納骨しなければ成仏できないという決まりはありません。
ただし、宗派やお寺によっては自宅供養や手元供養を良しとしない場合もあります。そういった場合は、先祖代々のお寺(檀那寺)に相談し、意向を確認しておくと安心です。
手元供養の主な3つのタイプ
手元供養にはいくつかの種類があり、ライフスタイルや気持ちに合ったものを選ぶことができます。
① ミニ骨壺タイプ(最も一般的)
自宅の仏壇横や棚に置ける小型の骨壺タイプ。名前や命日を刻印できる商品もあり、見た目もコンパクトでシンプルなものが多いです。

② 遺骨アクセサリータイプ(身につける供養)
遺骨をほんの少量だけペンダントやリングなどに納めて、常に身に着けられるタイプ。人目にもわかりにくく、近年特に人気が高まっています。

③ インテリア供養タイプ(お地蔵さんや仏壇風)
仏壇の代わりとして使えるようなインテリア性の高い置物に遺骨を納めるタイプです。お地蔵さんの像や、小さな仏壇セットなどがあります。

まとめ:あなたに合った手元供養の形を見つけよう
手元供養は、故人をいつも近くに感じながら生活するための新しい供養の形です。
法律的にも、仏教的にも基本的には問題なく、自分らしいスタイルで供養することができます。
大切なのは「自分がどう供養したいか」という気持ちです。
どのタイプがご自身やご家族の想いに寄り添えるか、じっくりと考えて選んでみてください。