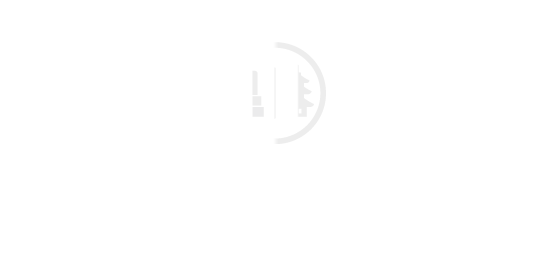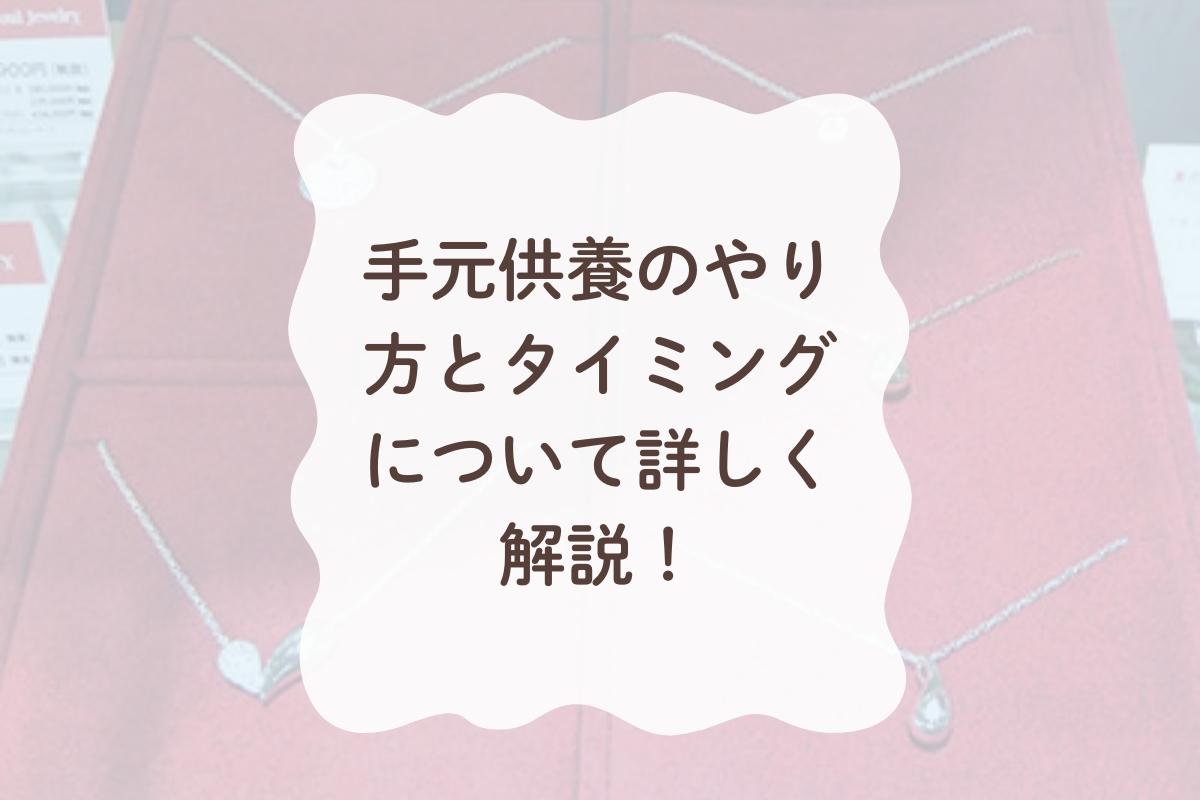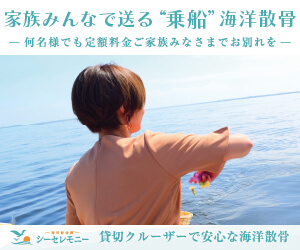「手元供養を購入したけれど、いつ・どうやって遺骨を移せばいいの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、手元供養の方法やタイミングについて、特に人気のあるミニ骨壺タイプとアクセサリータイプを中心に、わかりやすく解説していきます。
手元供養のやり方・方法
購入経路について
手元供養の商品は、以下の場所で購入できます:
- オンラインショップ
- 仏壇・仏具店
- 墓石店(石材店)
- 葬儀社
オンラインショップが最も手軽ですが、実際に商品を手に取って選びたい方は、仏壇店や石材店へ行くのもおすすめです。ただし、店舗に希望する商品が展示されていない場合もあるので、事前に問い合わせてから来店しましょう。
まずは手元供養のやり方・方法について、購入経路から説明します。
ミニ骨壺に遺骨を納める方法

火葬後に渡される骨壺は5〜7寸ほどの大きなサイズで、自宅での保管には不向きです。
そこで、小型のミニ骨壺を使って、手元供養を行う方が増えています。
手順
- 骨壺から遺骨を取り出す
- 割り箸などを使って少量の遺骨を移す
- 遺骨は直接入れるのではなく、白い布(さらしなど)で包んでから封入する
※商品によっては、封入用の道具が付属している場合もあります。
アクセサリーに遺骨を納める方法

手元供養用のアクセサリーには、以下の2種類があります:
- ペンダントやブレスレットに小さな穴が空いており、そこに遺骨を入れるタイプ
- 遺骨を粉砕して作る、メモリアルストーンタイプ(業者依頼が必要)
この記事では、前者の自分で遺骨を納めるタイプの方法をご紹介します。
手順
- ペンダント裏などのネジを開け、小さな穴を見つける
- ピンセットで米粒ほどの遺骨を入れる
- 骨が大きい場合は、指で軽くつぶすか、骨壺内の粉状の遺骨を使用する
※納められる量はわずかですが、いつも身に着けて故人を感じられるのが特徴です。
手元供養のタイミングについて
手元供養を始めるタイミングは、大きく分けて以下の2つです:
- 火葬後、自宅で骨壺を保管している間
- お墓や納骨堂へ納骨するタイミング
おすすめは、自宅で保管している間に、落ち着いて自分の手で行うことです。
特に遺骨アクセサリーは細かい作業になるため、納骨当日など慌ただしいタイミングは避けましょう。
よくある質問:「四十九日までにしてもいいの?」
四十九日が選ばれるのは、仏教的な意味合いもありますが、集まるタイミングとして都合が良いという理由もあります。
実際は、一周忌や三回忌に納骨される方も多く、手元供養も四十九日までに行う必要はありません。
手元供養のその後について
自宅で遺骨を安置するのは合法ですが、埋葬することは法律違反です(墓埋法による)。
また、将来的に別の場所へ納骨を考えている場合は、「分骨証明書」を取っておくのがおすすめです。
火葬場や霊園管理事務所で発行してもらえるので、必要なタイミングで相談してみましょう。
理想的な手元供養の終え方
- ご自身の火葬時に、手元供養品も一緒に火葬してもらう
- もしくは、お墓や納骨堂に一緒に納めてもらう
※手元供養品によっては火葬できない素材もあるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
この記事では、手元供養のやり方・タイミング・注意点について詳しくご紹介しました。
手元供養はとても繊細な供養の方法です。
「正しいやり方」は人それぞれですが、大切なのは故人を思う気持ちです。
少しでも不安や疑問が和らぎ、自分らしい供養ができるお手伝いができていれば幸いです。
海洋散骨の資料請求